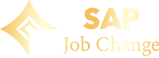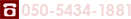投稿日:2021年10月4日
【コンサルティングファームでのケーススタディ面接における心構え】
はじめに
コンサルティングファームの面接において、最も身構えてしまうのがケーススタディ面接ですよね。
SAPコンサルタントの面接においては、それほど課せられることはないかもしれませんが、それでもいくつかの企業においては実施していますし、特にSAPコンサルタントから戦略コンサルタントを目指す場合には、ほぼ必須であると思っても良いでしょう。
ケーススタディ面接は、その場で突然始まることもあるので、SAPコンサルタントとして転職する場合であっても、準備をするに越したことはありませんし、実際に準備を全くせずにケーススタディ面接をされて撃沈してしまったというケースもよくあります。
しかしながら一方で、新卒であれば対策する時間を十分に取ることができますし、それ専用のセミナーも多数開催されているので、じっくりと準備して面接に臨むことができますが、中途採用ではそう簡単にはいきません。
ほとんどの方が働きながら準備をしなければならないので、対面でケーススタディ面接の対策をする時間を確保することが難しく、自力で準備をしなければいけないことも想定されます。
そういう場合には、書籍を購入するなどして、「ケーススタディ面接はどんな感じなのか」と調べると思いますが、結局のところ受かるためのポイントがなかなか掴みづらいという声も多く、どのように準備すればよいか分からないことも良くあると思います。
そこで今回の記事では、ケーススタディ面接に焦点を当て、実際に戦略コンサルティングファームで面接官を経験していた方の話を参考に、面接官が何を見ているのかをお伝えしたいと思います。
なお、本記事は大まかなポイントについての整理となりますので、導入として参考にしていただければと思います。具体的な回答方法などについては書籍などをご活用ください。
フェルミ推定を課されることはほとんどないが、対策は意外と簡単
ケーススタディ対策として有名なのがフェルミ推定です。
フェルミ推定とは、実計測が困難な数や個数の推測値を答える問題であり、例えば「日本に電柱は何本あると推測できますか?」や、「アメリカのシカゴには何人のピアノの調律師がいると推測できますか?」などがよく知られている有名な問題です。
ケーススタディ面接の対策をする際に、このフェルミ推定ばかりをやろうとする方がいますが、実際のところフェルミ推定が課されることはほとんどなく、ケーススタディ面接を実施する企業の中でも、20~30社に1社ぐらいではないかと思います。
ひと昔前はよく出題されていましたし、Google社でもフェルミ推定を出題することがありましたが、Google社が自社の社員のパフォーマンスを調査したところ、フェルミ推定の出来との相関関係が無いという結論に至り、廃止をしたという背景があります。
その話が広まってからは、特に出題頻度は減りました。
しかし、あくまでも頻度が減ったというだけであり、実際に大手有名コンサルティングファームでたまに出題されたということは聞くので、対策をしていて損はありません。
対策する際のポイントとしては、「好き勝手仮説を立ててしまっても良い」ということです。
例えば、「アメリカのシカゴには何人のピアノの調律師がいると推測できますか?」という問題に対して答えを知っている人はいないでしょうし、それは面接官も同じです。
つまり、その推測値が正しいかどうか面接官は判断できないのです。
では何で判断するのかというと、どのようなプロセスでその結論を導いたのかということです。
この問題の場合は、シカゴの人口や、世帯数、ピアノが置いてある割合などの掛け算によって導くのが一般的ですが、シカゴの世帯数とか、ピアノが置いてある割合なんて面接官が知っているわけがありません。
(調べていたら別ですが、正確な数字を見たいわけではないので、恐らく面接官は調べていないでしょう。)
なので、それぞれの数値は正しくなくても良く、自分で勝手に予想しても問題ないのです。
それよりも、どのような要素の掛け算で導いているのかが重要なのです。
実際に、それぞれの要素の数値が、現実とは大きくかけ離れているものを利用して回答してしまった方がいますが、そのプロセスに納得感があったということで通過になっています。
フェルミ推定は、ぱっと見で難問に見えてしまいますが、勝手に数値を予想しても良いぶん、慣れてしまえば意外と簡単なので、プロセスの導き方をしっかりと理解しておきましょう。
ビジネスケース問題に重要なのはイノベーションを起こせるか
ビジネスケース問題を使ったケーススタディ面接は、多くのコンサルティングファームで実施されており、SAPコンサルタントであっても3社に1社ぐらいは遭遇する可能性があります。
ビジネスケース問題とは、実際にあった、もしくは、架空の事例に対して、あなたであればどう考え、どう行動するかを問うものです。
例えば、「家電量販店が自社ブランドのスマートフォンを販売する際の販売戦略を考えてみてください」や、「カフェの売上を1.5倍にするためにはどうすれば良いと思いますか」などがビジネスケース問題です。
こういうビジネスケース問題が出題されると、とにかく正解を出そうとする方がいますが、正解はそう簡単に出ませんし、フェルミ推定と同じく、面接官も正解と言えるものは分からないでしょう。
重要なのは、導き出した回答が正しいかどうかではありません。やはりここも思考プロセスを最も見られており、回答に至るまでの考え方がロジカルかどうかがポイントなのです。
したがって、ビジネスケースの場合であっても、明確に示されていない数値に対しては、自分で好きに仮説を立てても問題ありません。
とは言っても、適当な回答でも良いというわけではなく、どのような回答が導き出されるのかはジャッジの対象となっており、特に面接官が見ているポイントは、イノベーションを起こせるかどうかということです。
これは実際に某外資系コンサルティングファームの戦略コンサルタントの方が、面接で重視しているポイントということで聞いたことがある話ですが、ネットで調べれば出てくるようなありきたりの回答は期待していないとのことことでした。
考えてみればもっともなことで、クライアントの課題の解決策をネットで調べて、その内容を提案するということはまず無いですよね。
それに、一般的に知られているような方法で解決するのであれば、わざわざ高い報酬を払ってコンサルタントに依頼する企業もないでしょう。
ここで言うイノベーションとは、今までに無かったような新しい考え方であり、面接官としては、テンプレート通りの回答ではなく、革新的な独自の回答を期待しています。
よって、ビジネスケース問題が出題されたときは、既存の考え方に捕らわれることがないように意識しておくとよいと思います。
まとめ
今回の記事では、コンサルティングファームでのケーススタディに対する心構えをお伝えしました。
ケーススタディ面接で重要なのは正解を答えることではありません。なぜそのような回答に至ったのかのプロセスが重要です。
フェルミ推定であっても、ビジネスケース面接であっても、意外と対策としてはシンプルなので、物怖じせずにしっかりと準備して面接に臨みましょう。